私は臨床実習生を受け持ったことがあります。
どんな学生も私が「質問するね」というと渋い顔をしていたように思います。
慣れていない環境、慣れていない場所、そして何を質問されるかわからない
こんな状況じゃ不安になるのも仕方ないですね。
そこで今回は、私が臨床実習生を受け持った際に意識していることをあげていこうと思います。
実習全体を通して意識していたこと
臨床工学技士の仕事は楽しいと思ってもらえるように
私が一番重要視していた点です。
「臨床実習」は学生が現場を長期間体験できる貴重な場になります。
そんな中、現場の臨床工学技士たちがシーンとして、苦しそうに仕事をしていたらどういった印象を受けるでしょうか。
きっといい印象は受けないと思います。
- ここの病院はやばいな
などの印象だったらまだマシです。これが、
- 臨床工学技士の仕事ってつまらなそうだな
と、思われてしまった場合、その学生にとっては
臨床工学技士の仕事=つまらない
となってしまいます。
ただでさえ、まだまだ発展途上で数が少ない臨床工学技士
学生がそんなことを思ってしまうのはもったいないです。
そのため、楽しく仕事をしているところを見せてあげることが一番の実習だと思っています。
ポイントは「楽しく仕事をしている」点です。
サボってゲームをしている等は論外です。
質問するときに意識していたこと
学生に考えてもらう
どのくらいのことを知っていて、どこからが知らないことなのか。
これが非常に重要だと思っています。
いきなり、学生のレベルより高い質問をしてしまうとどうなるでしょうか。
たとえば、
「○○を行う理由は?」
「わかりません。」
「じゃあ宿題ね。」
これだと味気ないしもったいないと思います。
そして宿題になった場合おそらく
- インターネットで調べる
- 参考書で調べる
- 学校の先生に聞く
等になると思います。
次に実習まで期間が短い(たいてい翌日)場合、たぶん調べた内容をそのまま何も考えずにノートやレポート用紙に書いて提出すると思います。
事実自分も実習中にでた宿題はそうでした。
参考書やインターネットで答えを調べて、そのまま提出してしまうと学生が「考える」時間が無くてもったいないように思えます。
そのため、本当に聞きたい質問より難易度が低く、関連性のある質問からしていきます。
こんな感じです。
「××をする理由は?」
「△△です」
「じゃあ○○をする理由は?」
「わかりません」
「ヒントは△△」
前に答えた質問がヒントになるため学生も考えやすい、と思っています。
臨床と結び付けてもらう
学校などで学んだことを実臨床に結び付けてもらうことも重要だと思っています。
私は学生時代、学校の勉強していたとき
「こんなのいつ使うんだよ!!」
と思って勉強していた科目が多数あります。
実際に現場に出てみてもそういった知識を使う場はほとんどありませんでした。
ほとんど、です。
逆を言えば使う時があるということです。
電気回路や力学、さらには数学なども使う時がありました。
たとえば
「生体情報モニタ」の波形が小さいといったトラブルがあった場合、
装置設定や患者さん要因が原因でない場合、機器の故障が考えられます。
そういった時、ただ「装置が故障しています」ではなく「装置内部の増幅器が故障している可能性がある」と言った考察ができます。
また、人工呼吸器回路や血液浄化装置の回路を延長したいと考えた時はハーゲン・ポアズイユの式が役立ちそうです。
このように、一見使わなそうな知識でも使う場面があります。
個人的には数学が苦手なため「もっと勉強しとけばよかった」と思うこともしばしば。
このような科目ですら使うことがあるということは、「臨床」科目は基本的にどんな知識でも使う可能性があります。
臨床工学技士の主な業務は「呼吸」、「循環」、「代謝」、そしてそれら機器を管理する「機器管理」がメインになります。「呼吸」、「循環」、「代謝」は密接に関係しており、それらを「医療機器」の観点からアプローチします。
そのため、これら科目はどんな業務に従事していても使用する可能性があります。
そういった学校で学んだ「知識」を、現場で「知恵」に昇華して使用しているところを教えてあげる必要があると思っています。
さいごに
個人的の意識している点を書かせていただきました。
これから臨床実習を控えている学生の方や臨床実習を引き受ける施設の方の一助になればと思っています。
それでは、楽しく臨床実習を行っていきましょう!!
学生目線の臨床実習について↓
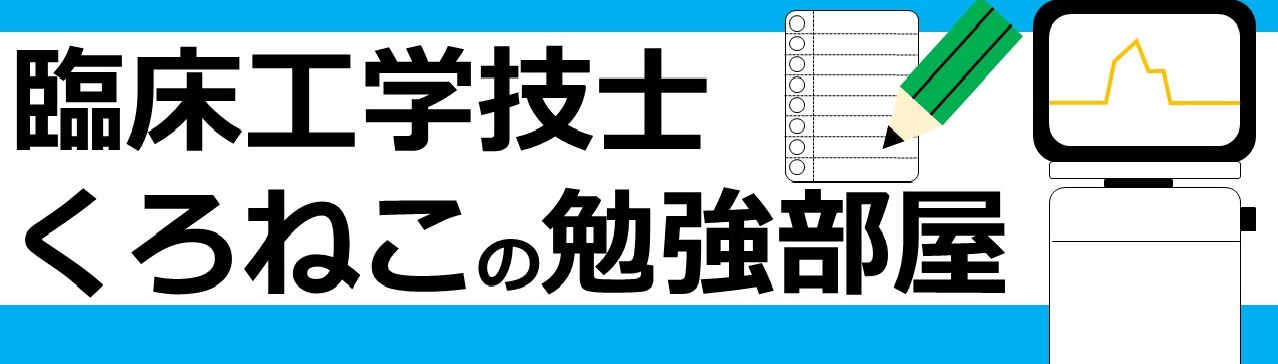






















コメント