呼吸療法に関連する必要な知識は多数あります。
呼吸生理・換気モード・グラフィック波形などなど勉強しなければならない項目をあげればきりがありません。
そこで今回、呼吸療法関連の勉強をする上でおすすめな本を臨床工学技士目線で紹介していこうと思います。
呼吸生理

まずは呼吸生理!!
ウエスト呼吸生理学入門 正常肺編

呼吸生理を極めたい人におすすめです!!
呼吸生理学のみで200ページ超の傑作です。
しかも、「疾患肺」編が別途あるため、純粋な呼吸生理学で構成されます。つまり、本書は圧倒的なボリュームになります。
どんな本?いいところ・悪いところ
圧倒的なボリュームから呼吸に関わる人すべての人におすすめしたいのが本書になります。また、各章に最後に設問があるため、自分の理解力の確認もできます。
しかし、本書は翻訳本になるため、若干言葉が頭に入ってきにくいため注意が必要です。

翻訳本だからしかたないね・・・
内容が非常にボリューミーであり、難しい内容も含むため理解するのが難しいかもしれません。が、逆を言えば圧倒的な内容量のため、非常にマニアックなところまで物理学などを用いて式やグラフを駆使してのっているため、呼吸生理が網羅されていると言っても過言でははありません。数学や物理、化学が苦手な方は少し嫌悪感を感じてしまう可能性はありますが・・・・
「ウエスト呼吸生理学入門 正常肺編」と「ウエスト呼吸生理学入門 疾患肺編」がリンクしている箇所もあったりするため交互に行き来して勉強する、といった使い方も可能です。
また、本書は2009年発売で若干古いですが、第二版が2017年に発売され、15ヶ国語で翻訳される名著中の名著になります。

じっくり呼吸生理を勉強するならこの一冊で決まり!!
辞書・お守りとして持っておきたい一品!!
ウエスト呼吸生理学入門 正常肺編
ウエスト呼吸生理学入門 疾患肺編

学会やセミナーなどでも本書の引用はよく見かけます!!
Oxygen マリノが提案する新しいパラダイム

まさかの酸素に関する呼吸生理特化本!!
索引込みで247ページ!!

酸素だけでここまでの量はすごい!!
どんな本?いいところ・悪いところ
人工呼吸器・呼吸療法ではかかせないモノ、それは酸素です。その酸素が
- どれだけ有害か
- どれだけ大切か
などがひたすら書かれています。そのため当然マニアックな内容になります。読んでて

へぇ、なるほど!!
と唸ることが多々あります。翻訳本にもかかわらず、読みやすいのも特徴です。

酸素について深く知りたいマニアックな方は読んでみるのもありです!!

目指せ!!酸素マニア!!
呼吸療法全般

次は呼吸療法全般について!!
これならわかる! 人工呼吸器の使い方 (ナースのための基礎BOOK)

呼吸療法業務に関わる初学者におすすめです!!
- 人工呼吸器の流れを知ろう
- 呼吸不全への初期対応
- 酸素療法
- NPPV
- HFNC(ネーザルハイフロー)
- 気道確保
- 人工呼吸器の設定
- 人工呼吸器患者の状態管理
- 人工呼吸器からの離脱
と、「呼吸療法」全般について200ページ超で記載されています。
どんな本?いいところ・悪いところ
本書を読んだ感想ですが、率直に言うと

これはやばい!!めっちゃわかりやすい!!
でした(語彙力)。
一番最初にある「人工呼吸器の流れを知ろう」と各項目冒頭部に「漫画」があります。「漫画」形式でイメージをつかんでから各項目の勉強ができるため頭にスッと入ってきます。また、解説ページもイラスト・写真が多数ある点も高評価です。
私の中で

「1年目の時に欲しかった本ランキング」ナンバー1!!
です。
呼吸生理から酸素療法、NPPV、換気モードからフィジカルアセスメントや栄養管理、人工呼吸器の離脱まで幅広く網羅されています。たとえば人工呼吸器やHFNCの回路組み立て方法や各物品の役割、NPPVとは、HFNCとはなど基礎的な部分から記載されています。そのため、特に人工呼吸器が苦手な看護師さんやICU業務を始めたばっかりの臨床工学技士に特におすすめです。
しかし、グラフィック波形や換気モードを深く知りたい人などは少しもに足りないと思います。そういう本が欲しい人は「人工呼吸器」のみに特化した本にしましょう。
また本書で使用されている写真は、NPPVではV60、挿管用人工呼吸器ではV500のため、自分の施設でもし採用されていればさらにイメージが付きやすいと思います。
さらに本書の付録として「グラフィックモニター早わかりポケットカード」があります。
これは
- グラフィックの基本
- グラフィックの異常波形
- 換気モード別グラフィック
- NPPVの換気モード
- 基本の換気設定
が簡単に記載されています。

ポケットに入るサイズのため、人工呼吸器に慣れていない時はポケットに忍ばせましょう!!
レジデントのためのやさしイイ呼吸器教室 ベストティーチャーに教わる全29章

呼吸療法業務に関わる人におすすめです!!
呼吸療法全般についての本であり、この一冊で呼吸療法の基礎は網羅できるかなと思いました。
どんな本?いいところ・悪いところ
本書は
- フローボリュームカーブ
- 血液ガス
- 胸部画像
などの検査についてや
- 人工呼吸器のモード
- 疾患について
など幅広い内容が記載されているのが特徴になります。
しかし、ほかのいわゆる人工呼吸器に特化した本と比べると、換気モードや設定についての内容など少し薄いなと感じてしまいます。

がっつり深くというより、広く・浅く!!
しっかり人工呼吸器について学びたいという人には向かないかなと思いました。
やはり、「ひろく、あさく、わかりやすく」がコンセプトになっているため

本書で基礎をしっかり勉強して、気になるところや更にしりたいことなどは別の本で勉強する
といった使い方がいいかなと思います。
まずは呼吸療法の基礎について知りたいという方におすすめです。
内容的には「3学会合同呼吸療法認定士」のテキストに近いかなと思います。
「3学会合同呼吸療法認定士」関連記事↓
また、本書は書籍版に電子版が付いてきます。
書籍の一番最後に、パスワードが載っており、PCでも見ることが可能になります。

書籍を持っていなくても、どこでも見れる!!
これは大きな利点だと思います。
人工呼吸器全般

次は人工呼吸器について!!
Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理

人工呼吸器に関わる人におすすめです!!
呼吸不全の考え方から始まり、酸-塩基平衡や各種換気モード、人工呼吸器の設定、グラフィック波形、更には充実したCase studyです。

やはりCase studyは魅力的!です!
0-11章とCase study、索引込み378ページ構成。
どんな本?いいところ・悪いところ
本書は第0章に「Dr.竜馬の人工呼吸10箇条」があります。人工呼吸管理に必要な考え方で、本書は10箇条に沿って構成もされています。
Dr.竜馬の人工呼吸10箇条
1.「呼吸=肺」とは考えない
2.SpO2だけで重症かどうかを判断しない
3.気管挿管と人工呼吸は分けて考える
4.人工呼吸はモードよりも設定にこだわる
5.人工呼吸器は肺をよくしないが、悪くはできることを知る
6.人工呼吸管理中には、正常な血液ガスを目標にしない
7.人工呼吸器に患者を合わせるのではなく、患者の呼吸に人工呼吸器を合わせる
8.呼気に注意する
9.人工呼吸器は診断にも使う
10.患者の回復をあなどらない
Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理 第0章 人工呼吸器10箇条

上記は非常に大事な考え方だと思います!!
また、イラストも大量にあり、とても分かりやすいです。

この一冊で人工呼吸器関連の本は十分じゃないかとも思ってしまうほど情報量!!
そのため、人工呼吸器関連の本で最初の1冊に使用するのはもちろんのこと、その後も長く活用することができます。

私も長く愛用しています
さらに各項目でレベル分けがされています。
★☆☆:すべての人向け
★★☆:基本がわかって、少しステップアップしたい人向け
★★★:もっと人工呼吸器を使いこなしたい人向け
と、3段階のレベルで分かれているため、今の自分のレベルに応じて勉強すべき点が明確にわかります。

勉強しやすくて非常にありがたい!!
さらに最後に豊富なCase study(9症例)があるため、自分へのテストとして活用することにより、自分の習学度合いが図れる点もいいと感じました。
難点としてしいて上げるなら本書がでかくて重いことです。

自宅学習用に使いましょう!!

初学者~人工呼吸器ガチ勢まで、幅広く支持されています!!
人工呼吸の考え方 いつ・どうして・どのように

人工呼吸器に関わる人におすすめです!!
計17章構成、索引込みで271ページになります。
呼吸生理から人工呼吸器の設定、換気モード、グラフィック波形、症例に対する対策と
「人工呼吸器に関する基礎」を網羅した一冊になります。
どんな本?いいところ・悪いところ
イラストが多く、難しいこともたとえ話を駆使して教えてくれる一品。ですが、まったく知識がない状態や最初の1冊となると少し難易度が高いかも。

私は2年目の時に購入して、この本で人工呼吸器を勉強しました。
そのため、私にとっての「人工呼吸器のバイブル」に近いかもしれません。
しかし、2年目当時(人工呼吸器学び始め)の時にこの本で勉強を始めた時に難易度が少し高いなと感じていたことも事実です。なので、本書を読む前にもう少し簡単な本でとっかかりを作るかしたほうがいいかもしれません。
また、本書の発行は初版が2009年と古いものになっています。そのため、若干情報が古かったりしますが、基本的には問題にならないと思います。
さらに本書はたとえ話が秀逸なため、新人教育する側のヒトも本書はおすすめです。風船、ホース、車、たき火、勉強、山、ボクシングなどなど、身近なことでたとえ話をしてくれます。そのたとえ話を大量のイラストや図で説明してくれます。本書では200近いイラストや図を用いています。

開けばだいたいイラストや図が1~2つある計算になりますね。
人工呼吸器に慣れていない新人に人工呼吸器とは何なのか、何故つかうのか、どう動くのかなどイメージを持ってもらうために参考にするには最適だと思います。
あと、地味にいいところは実は本のサイズが小さいことです。
※さすがにポケットには入りませんが・・・・。
なので、

病院に持っていき、気になった点を病院で確認する
といった使い方を私はしていました。

自宅には「Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理」、病院では「人工呼吸の考え方 いつ・どうして・どのように」というスキを生じさせぬ2段構え!!
換気モード

お次は換気モードについて!!
早わかり人工呼吸器換気モード超入門

換気モードが苦手な人におすすめです!!
人工呼吸器の基礎、各種換気モード、グラフィック波形などを含めた内容で141ページ。
どんな本?いいところ・悪いところ
換気モードについて、イラストを多用して説明してくれています。
1ページに最低1個はイラストが使用されるくらいイラストが多用されているため、人工呼吸器に苦手意識がある人もすいすい読めるのではないかと思います。
しかし、人工呼吸器の使い方、呼吸ケアについての記載はほとんどないのが難点です。あくまで
- 換気モードが苦手
- グラフィック波形が苦手
という方向けの本になります。
わかりやすく換気モードを伝えるため、各換気モードで「例えるなら?」の項目があり、たとえ話が秀逸だと思います。
エスカレーターやアルバイトなど、身近なものに例えてくれるため、非常にイメージがしやすいです。

人工呼吸器が苦手な人におすすめなのはもちろんのこと、換気モードなどを教える立場の人にもおすすめです。
院内や部署内の勉強会を実施するときに

どうやって教えようかなー
と悩んでいる人は是非。
私も後輩教育などで本書を活用しています。
また、ポケットに入る「グラフィックモニタ異常波形Pocket Book」が付録でついてきます。
本当にポケットに入るサイズで便利ですが、回路構成の写真がニューポートe500を用いており、人工呼吸器が古いのが残念です。
INTENSIVIST Vol.10 No.3 2018 (特集:人工呼吸器)

換気モードを極めたい人におすすめです!!
上級者向き!!
人工呼吸器関連障害、患者-人工呼吸器間の非同調やA/C、SIMV、PSVをはじめ、BIPAP、APRV、PRVCやNAVA、PAV、更には自動ウィーニングまで記載があります。
INTENSIVISTは日本集中治療教育研究会(JSEPTIC)が年4回発行しています。本書は「人工呼吸器」特化の本になります。313ページ、主に換気モードを中心に構成されています。
特に「換気モードの応用」について記載されています。
どんな本?いいところ・悪いところ
本書の特徴としては各章、各著名な先生方が大量の引用文献を用いて説明している点だと思います。それ故に内容が非常に難しくなっています。

基礎的なことを理解してからのステップアップ本!!
そのため、人工呼吸器に関して基礎的なことを一通り勉強した次のステップには最適ではないかと思います。
一般的に言われていることや(2018年発売時点の)最新の知見など、文献をもとに説明してくれるため説得力が段違いです。
VCやPC、PRVCなど各送気方式やA/C、SIMVなどの基礎的なモードについても生存率や使い分けなど、文献ベースで記載されています。また、経肺圧やVIDDなどやNAVAやPAVや自動ウィーニングなど比較的新しいモードについての記載があることもうれしいです。
特に新しいモードについては記載されていない参考書も多く、
- 直接メーカーに聞く
- 学術集会や講演会へ参加
などしないと情報が得られないため、本書が非常に役立ちます。

最近はWebも増えて参加しやすくなりましたが・・・
さらに、換気モードのみならず「呼吸仕事量」や「患者-人工呼吸器非同調」についても文献ベースの話があることが特徴です。文献ベースから人工呼吸器について知りたい人におすすめです。
※各メーカーの人工呼吸器のスペック表なども載っているところもうれしいです。

人工呼吸器ガチ勢のための一冊!!
グラフィック波形

続いてグラフィック波形について!!
え!?ここまでわかるの?人工呼吸器グラフィックス

グラフィック波形を極めたい人におすすめです!!
上級者向き!!
- 人工呼吸器グラフィックスと臨床応用
- 圧-容量ループと流量-容量ループ
- 一般的な人工呼吸器モードのためのグラフィック波形
- 圧規定換気と量規定換気
- 臨床所見
- 新生児・乳幼児
- 症例検討
と、なっています。最初から臨床応用とはなかなかすごい本ですね。索引込みで150ページ構成となっています。
どんな本?いいところ・悪いところ
教科書の補足として活用することがコンセプト。実際に臨床現場ですぐに使えるように「持ち運びできる参考書」を目指しているためコンパクトなまとまりになっています。
※コンパクトと言っても、おそらくポケットには入りません。
グラフィック波形の基礎から応用までのっている本。もちろん、ループ波形も掲載されています。各種異常波形も多数のっているため、本書で一通り勉強した後、ベッドサイドに置いて異常波形が出た時に参考にする、という使い方がいいかもしれません。
しかし、翻訳本のため、若干日本語的に読みにくいところもある。

圧倒的にグラフィック波形に特化された本。マニアックな話もあり、非常に面白い。
これを読んで理解できればグラフィック波形は大丈夫というレベル。

逆を言えば本書からグラフィック波形の勉強をスタートするのはあまりにも無謀
グラフィック波形特化型の本ということもあり、非常にたくさんのグラフィック波形が掲載されています。換気モード別のグラフィック波形、患者-人工呼吸器非同調、コンプライアンスの変化、エアートラッピング・・・などなど、多岐にわたって紹介されています。
また、新生児のグラフィック波形も紹介されています。なかなか新生児のグラフィック波形が載っている本は少ないのではないかと思います。
付録として新生児の症例検討もあり、なかなか解きごたえがあります。
もちろん、成人領域の症例検討もあります!

最後の理解度チェックテストとして活用もありですね。
アラーム・トラブルシューティング

続いてアラーム・トラブルシューティングについて!!
Table Top Exercise(机上演習)で学ぶ人工呼吸器トラブルシューティング
人工呼吸器のトラブルシューティング(グラフィック波形、アラーム対応)に特化しており索引、あとがき込みで197ページです。

人工呼吸器が苦手な人におすすめです!!
人工呼吸器に関わるけど、人工呼吸器が苦手な人必見!!1冊でトラブルシューティングが分かる仕上がりになっていると思います。
どんな本?いいところ・悪いところ
人工呼吸器のトラブルシューティング特化本。
トラブルに必要な人工呼吸器の異常グラフィックやアラーム対応について「がっつり」書いてあります。

どういう形式で書かれているの?
アラーム別に「Yes」、「No」のフローチャート形式で書かれており、最終的にどのような「対処」をすればいいかにたどり着きます。
フローチャートは
- レベル0:急激な血圧低下、心停止→人工呼吸器のトラブルシューティングの範疇を超えるため本書での取り扱いはありません。
- レベル1:「回路外れ、リーク、気管チューブの痰」など原因は危機的事象ですが発見が容易
- レベル2:「患者の気道抵抗、コンプライアンス変化、非同調」など病態の変化や人工呼吸器設定の見直しが必要
と分けられており、アラームが発生した時にレベル0→レベル1→レベル2の順番で確認していきます。
レベル1は見てすぐわかるような事象なため、サクッと確認します。サクッとみてもわからない場合、レベル2に移行します。レベル2は一目みてもわからないことが多いため、じっくりと考察します。
ここでトラブルの種類や原因を特定しています。このような流れのフローチャートになっています。

トラブルシューティングはフローチャート形式が分かりやすい!!
また、本書の最大の特徴は「机上演習」です。
本書は各項目にQRコードがついており、
そのQRコードを読み込んでパスワード(※パスワードは本書に記載されています)を入力すると波形の動画が大量に出てきます。
人工呼吸器のグラフィックが難しい点は波形をイメージしにくい点にあると思います。そのグラフィックを動画で確認できるため、イメージしやすくなっています。
NPPV

続いてNPPVについて!!
そういうことだったのか!!NPPV

NPPVが苦手な人におすすめです!!
- NPPVのしくみ
- マスクや回路などデバイスについて
- マスクフィッティング
- NPPVの実践
- NPPV vs HFNCについて
- COPD患者のNPPV
- 血液ガスについて
が記載されており、索引込みで156ページになります。
近年話題のHFNCについての記載があり、「NPPVとHFNCどっちがいいのか」など気になる題目があるのもうれしいです。
どんな本?いいところ・悪いところ

本書はNPPV導入本の位置づけ!!
となっており、初学者でもスッと頭に入ってくるような内容になっています。
さらに、
「マスクフィッティングを制するものはNPPVを制する」をコンセプトに
- マスクの形状や褥瘡防止
- マスクフィッティング、
- リーク
について力を入れて記載されています。

NPPVで一番困るところですね!!
さらにNPPV特有の換気モードである
- Sモード
- Tモード
- S/Tモード
などの解説が載っているところもうれしい点です。
また
- COPDに対するNPPV
- 血液ガス
について記載されているのもうれしいです。
特にCOPDの急性増悪に対するNPPVは強いエビデンスがあり絶対適応とされるため、そのような場面に出くわすことが多く、大変参考になります。
酸素療法

酸素療法について!!
INTENSIVIST Vol.10 No.2 2018 (特集:酸素療法)

酸素療法マニアになりたい人におすすめです!!
酸素の生理学
- イントロダクション
- 低酸素の生理学
- 呼吸調整のメカニズム
- 換気のメカニクス
- 肺胞から血流への酸素の移動
- 血流による酸素の輸送
- 酸素療法のモニタリング
- 酸素需給バランスのモニタリング
酸素療法の目標値
総論
- イントロダクション
- 高濃度酸素の弊害
各論
- 心停止蘇生後患者の酸素療法
- ARDS・急性呼吸不全患者の酸素療法
- 小児患者の酸素療法
- 脳卒中患者の酸素療法
- 心筋梗塞患者における酸素療法
酸素投与の方法
- 自発呼吸患者に対するマスク・カニューレによる酸素投与
- 経鼻高流量酸素療法high flow nasal cannula(HFNC)
- 高圧酸素療法
コラム:酸素供給源
コラム:酸素療法のコスト

もくじを見ただけで、内容のボリュームにびっくりしますね。
どんな本?いいところ・悪いところ
酸素療法についてこれでもかとか書かれた本書。
酸素の生理学からモニタリング、病態ごとの酸素療法について、挙句の果てには高圧酸素療法や酸素のコストまで、いわゆる「酸素療法の欲張りセット」です。
文献ベースで書かれているため説得力が段違いですが、「酸素療法」について勉強したい人の最初の一冊で本書を選ぶとたぶん絶望します。
内容が初学者には難しすぎると思います。そのため、ある程度知識がある方が更に酸素療法について勉強したい人が手に取る本だと思います。

個人的には「酸素の生理学」についてがっつり書いてあるところがポイント高いです。
生理学の本を読んでもここまで「酸素の生理学」について書かれている本はないのではないかと思ってしまいます。ただ、内容は普通に難しいです。

ガイドラインについてもまとめてあり非常に便利!!
また、臨床工学技士としては
- 自発呼吸患者に対するマスク・カニューレによる酸素投与
- コラム:酸素供給源
ここに注目かなと思います。酸素療法に使う各器具や酸素ボンベ、配管についてと臨床工学技士が関わるところがガツンと記載されています。
また、「コラム:酸素療法のコスト」は昔から気になっていたところだったので面白かったです。更に、近年HFNCが注目されているため、いわゆる「酸素の流しっぱなし」でどれだけコストがかかるのか気になっていました。

以上より、「酸素療法の欲張りセット」、これは過言ではないと思います。
胸部画像診断

胸部画像にについて!!
本当は教わりたかった ポータブル胸部X線写真の読み方 さくっと読めてガツンとわかる7日間特別講義

胸部画像診断が苦手な人におすすめです!!
ポータブル胸部X線の読み方について
- 読影
- カテーテル、チューブ類
- 浮腫、胸水
- 肺水腫
- 無気肺、肺炎
- 気胸
- ARDS
をメインに書かれています。また、補講として
- 外傷ポータブル
- 腹部単純写真
についても書かれています。
索引込みで270ページの構成です
どんな本?いいところ・悪いところ
本書は「サクッとよめてガツンとわかる」をコンセプトに作成されています。
そのため、初学者にとてもやさしい構成になっています。

私も導入本として本書を読みましたが、とても分かりやすかったです。が、残念ながら私は7日では読み切りませんでした。
どうしても「画像診断」は苦手意識を持ちがちだと思います。

そんな苦手意識を持っている人向き!!
しかし、決して本書を読めばすぐに画像が読めるわけではありません。
※読める人はいるかもしれませんが、私は読めませんでした。
「本書」で理解し、実際に画像を見てどうか、を行うことが大切だと思います。
そして、画像が読めてくるととても楽しくなってきます。是非、「画像が読めない」と食わず嫌いの方は手に取ることをお勧めします。
新生児

新生児の呼吸管理について!!
新生児の呼吸管理ハンドブック

新生児呼吸管理に関わる人(特に初学者)におすすめです!!
- 蘇生の実際
- 呼吸管理の実際
- 呼吸管理の実際
- 人工呼吸器による呼吸管理
- 呼吸管理中のモニタリング
- 呼吸管理に有用な特殊検査
- 呼吸管理中のケア
- 在宅呼吸管理
索引込み241ページ構成です。
どんな本?いいところ・悪いところ
圧倒的に「新生児の呼吸管理」に特化された本。
酸素療法や換気モード、さらには新生児特有の換気モードであるNAVAやHFOVまで記載があるのは非常にうれしいです。

NAVAに関しては挿管のNAVAからNIV-NAVA、更には別途、横隔膜活動電位(Edi)まで記載される優遇っぷり。
しかし、NAVAは新生児以外ではほとんど使わないモードのため、個人的には本書でもう少し詳しく知りたかったというのが本音。ですが、NAVAの適応や準備物品、初期設定やNAVAlevelのコントロールまで載っているため、初めて勉強する分には十分だと思いました。
また、HFNCについて記載されている点も良いと感じました。メーカーごとの装置の特徴からプロングの違いまで記載されています。
特にお気に入りは「HFNCとn-CPAPの使い分け」が載っている点です。

どう使い分ければいいのかな
と、個人的に思っていたところだったため知りたかったことジャストで勉強できました。
NAVApedia 新生児NAVAのすべて−チームでとりくむケアと実践

新生児NAVAに関わる人におすすめです!!
- NAVAの歴史
- 新生児とNAVA
- NAVAの基本としくみ,使い方
- NAVA,NIV-NAVAの看護
- NAVA,NIV-NAVA症例集
- NAVApedia The Q&A for NAVA
- NAVAいろいろ 〜となりのNAVA〜
- NAVAとファミリーセンタードケア(FCC)
- NAVA文献集
- 実際に使ってみよう! NAVAとNIV-NAVAの使い方[別冊]
と、10章構成になっています。

ついに出た、待ち望んだ新生児NAVA特化の本!!
どんな本?いいところ・悪いところ
本書は「新生児NAVA」特化の本。
どの書籍と比べても本書が一番新生児NAVAについて詳しく書かれています。

詳しく書かれているのに写真なども多数あり、わかりやすい!!
新生児NAVAをやっている施設なら持っておきたいところ。

分かりやすく書かれているのに、引用論文も多数あり!!
論文も多数記載されているため、ある程度NAVAに慣れた人たちも楽しく読むことができる一品だと思います。

新生児NAVA特化本のため、成人NAVAは記載されていないことにご注意を。
集中治療

最後に集中治療について!!
Dr.竜馬のやさしくわかる集中治療 循環・呼吸編

集中治療に関わる人におすすめです!!
本書はおおまかに「循環」と「呼吸」についてかかれています。
索引込み406ページになります。2020年発行のため、比較的新しい知見も多数載っています。
循環
- 敗血症性ショック
- 肺塞栓
- 高血圧緊急症
呼吸
- 気道管理
- COPD急性増悪
- 重症肺炎、ARDS

について詳しく記載されています!!
どんな本?いいところ・悪いところ
本書は図や写真が大量に使われていることがうれしい点です。更に、「研修医」と「指導医」の会話形式から詳細の説明に移行するため、イメージが付きやすいのもおすすめポイントになります。

量はあるけどわかりやすい!!
それが本書を読んだ感想です。
循環部門では「血圧」や「心拍出量」などの基礎的なところから記載されているため、初学者にも安心の構成です。
呼吸に関しても「気管挿管の適応」などからはじまり、High-flow nasal cannula(HFNC)を含む酸素療法についても記載があります。HFNCはROXインデックスなど、最新の知見も記載されています。
※ROXインデックス=SpO2/FIO2÷呼吸回数
また、人工呼吸器の換気モードなどについても記載があります。が、人工呼吸器特化の本とくらべると少し寂しいかもしれません。
これから集中治療室で勤務する人、すでに集中治療室勤務の人、双方におすすめの一品だと思います。
本書のコンセプトとして「研修医時代に聞きたかった内容」をコンセプトに作られているため、カルテの書き方など実は知りたかった内容も載っているのがうれしいです。
集中治療医学
細胞~各臓器にいたるまで「集中治療」に必要とされる「生理学」についての本です。索引込みで407ページの超大作です。
どんな本?いいところ・悪いところ
サイトカインやデリバリーO2、乳酸や酸塩基並行など集中治療といえば!!というような内容がガツンと記載されています。

ですが、やはり難しい・・・
全身臓器について幅広く書かれている、かつ、深い内容まで記載されているため、内容としては難しいと思います。

いきなり本書を読むと心が折れるかも・・・
別の本で生理学の基礎を固めた後、細胞から全身を含めた「生理学」を知りたい、という方にはお勧めです。

集中治療に関する生理学のため、「集中治療戦略」自体はほとんど記載されていません。
本気のおすすめ本

結局どの本がいいの?いっぱいあってわからない・・・
なんて声も聞こえてきそうです。そこで私のおすすめ本は・・・・
初学者
- これならわかる! 人工呼吸器の使い方 (ナースのための基礎BOOK)
中級~
- Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理
ガチ勢
- INTENSIVIST Vol.10 No.3 2018 (特集:人工呼吸器)
この3冊です!!
さいごに
臨床工学技士の目線から呼吸療法に関するおすすめ本を紹介しました。
おすすめ本を発見次第随時更新していきます!!
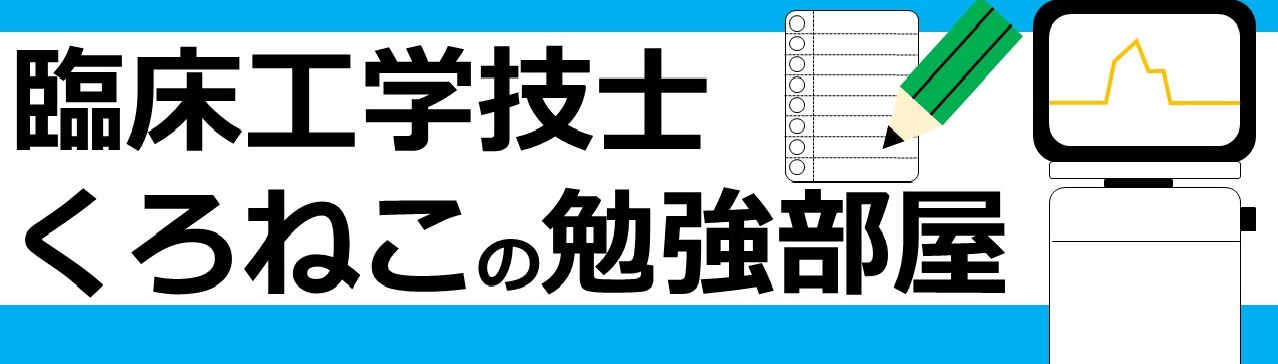






















コメント