医療機器メーカーの仕事とはいったいどのような職業でしょうか。また、臨床工学技士が医療機器メーカーに就職した時にメリットはあるのでしょうか。

医療機器メーカーの話を聞いてきたよ!!
まずは医療機器メーカーがどのような仕事をしているのか、確認していきましょう。
医療機器メーカーについて

営業
病院やクリニックへ製品を進めたり、納品したりします。病院に勤めている方が一番会う医療機器メーカーの人は「営業」。

短期間ですぐ購入に至ったり、逆に数年計画の長期スパンで購入など、購入までの期間は多岐にわたります。
トラブルの一次対応なども行ったりしますが、本業は「製品を売ること」。そのために
- 医師
- 看護師
- 臨床工学技士
- 事務
など、さまざまな職種に製品を進めます。
営業は基本的に担当施設が割り振られています。その担当施設を毎日まわる「ルート営業」が主体です。
基本的に医師や看護師と会うためにはアポイントメントをとります。

緊急手術や急変など、様々な要因により、アポどりしていても簡単には会えないことも・・・
実際に会って製品を進めなければならないため病院内で「ひたすら待つ」なんてことも・・・むしろアポ通り会えることの方が少ないと思われます。

結果、アポをとらずに会いに行く、なんてことも・・・
これが「医療機器メーカー」がアポをとらずに突撃してくる理由です。

特にコメディカルに対してはアポどりするのは少ないのではないでしょうか
アポをとっても会えない可能性が高く、会えなかったらリスケ・・・・何てことしていたら仕事が終わりません。
また、
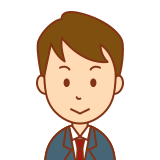
医療機器メーカー?とりあえず待たせといて大丈夫。
みたいな風潮があったりもします。
以上より、医療機器メーカーの営業は「予定通りにはいかない」ということも・・・
サービス・エンジニア
医療機器メーカーのサービス担当はそれら「医療機器の保守点検、修理」を行う職種です。保守契約などを結んでいると年1回ないし2回程度、医療機器のメンテナンスをします。
また、医療機器のトラブルがあった際には出動してトラブル対応や必要に応じて修理なども行います。

うーむ、臨床工学技士と同じようなことをしていますね。
しかし、臨床工学技士と比べ、担当エリアがべらぼうに広いことが特徴です。

全国で数人しかサービス担当がいない、なんていうメーカーも・・・
なので業務時間が「移動時間」に割かれることもしばしば・・・

もうちょっとだけ詳しく!!
サービス・エンジニアの主な仕事は
- 保守点検
- 修理
ですが、保守点検、修理には当然お金が発生するため
- 見積作成
もします。
また、トラブル発生時には
- 機器の故障なのか、手技の問題なのか
など原因調査を行います。基本的に第一報は電話でくるため、電話での聞き取り調査が重要になります。

片道1時間以上、なんてこともザラです。原因が「電源コンセントが抜けてました」では笑えません。
電話対応で解決できれば良し、解決できなければ診療などが滞ってしまう可能性があります。その場合は早急に現地に向かいます。
現地で原因調査や修理を行い、解決できればいいですが解決できなかった場合は困りものです。その時は機械の引き上げになりますが、代替え機がないと病院も困ってしまいます。
そのため、現地に向かう際は代替え機を準備してきます。言わば「お守り」です。また、代替え機の点検や、どの病院に持って行ったかなどの管理も行う必要があります。
そうしないと、
- いざ持って行ったときに機械が壊れていた
- どの病院に貸したかわからなくなる
などの問題が発生します。
また、トラブル対応をしているとその日に予定していた点検ができなくなってしまう可能性もあります。そのため、トラブル発生時は時間管理がとてもシビアになります。
- トラブルの原因と改善にかかる時間
- 病院までの移動時間
- 対応後、次の施設までの移動時間(点検に間に合うか)
など計算し、すぐに予定を立てる必要があります。
トラブルが無ければ、その日に予定されている保守点検、修理などをこなします。
基本的に保守点検は現地で行います。日程は基本的に営業が病院と話し合って決めます。
だいたい、数週間前から日程調整をしますが、なかなか日程が合わなかったり、返答がない時は大変です。予定が組めません。
現場での点検が終われば、会社に帰ってきて見積作成などの事務作業を行います。つまり、何事もなければ定時帰宅も可能ですが、トラブル対応などあれば残業になります。
また、サービスエンジニアは保守点検や修理する機械が無ければお仕事になりません。そのため、「保守点検」を推進する必要があります。保守点検、オーバーホールの必要性などを病院側へ伝えるのも1つ
アプリケーションスペシャリスト
製品紹介や学術集会への参加、医療機器の取り扱い説明、論文説明等をする人。

「クリニカルスペシャリスト」や「営業サポート」なんて言ったり。
呼び方はメーカーによって様々だと思います。
医療機器のスペックのみならず、
- 実臨床ではどうか
- 他施設ではどうか
- 文献ではどうか
など、特定の機器に対して幅広い知識が必要になります。

イメージ的には「営業」と「サービス」の間の位置づけ。

アプリケーションスペシャリストはどんな仕事をするの?
- 医療機器に関するプレゼンテーション
- 医療機器の操作説明
- 機器導入後のフォロー
- 社内教育
- 学会の展示ブース
- セミナーの企画、立案
- 販売促進のための企画立案
- 文献調査
- 施設側のトラブル、要望、疑問などの解決
などなど。機器の販促のため、営業とタッグを組みます。

求められるのは「プレゼン・パワーポイントスキル」です。

臨床工学技士はアプリケーションスペシャリストに向いているの?
個人的な意見ですが向いていると思います。
循環器関連(ペースメーカとかアブレーションとか)のアプリケーションスペシャリストは看護師さんや臨床検査技師さんも多い印象ですが、臨床工学技士もたくさんいます。
また、臨床工学技士は循環器領域のみならず、呼吸、代謝など幅広い知識を有しているため、医療機器メーカの選択肢はたくさんあるため、メーカーの選択肢が多いのが特徴です。

自分が得意な領域から選びましょう。
もちろん、ある程度の臨床経験がなければ意味がありません。そのため、アプリケーションスペシャリストの方たちは一定期間病院で働いていた人たちが多い印象です。
さらに、先生やコメディカルの方たちへ説明をするため、
- プレゼンテーションが苦手
- 資料作りが好きではない
などの方、アプリケーションスペシャリストはおすすめできないと思います。
臨床工学技士が「医療機器メーカー」に就職した時のメリットはあるの?
臨床工学技士の資格はメリットになる?
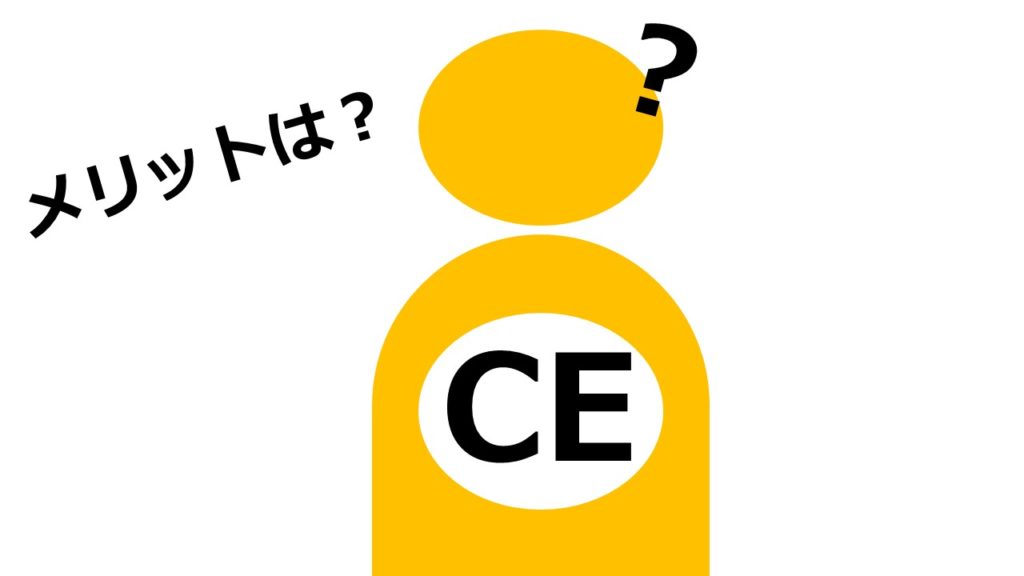
結論から言うとメリットはあります。「営業」、「サービス」、「アプリケーションスペシャリスト」業種を問わず、メリットはあります。

どんなメリット?
医療機器に関する基礎知識があるため、臨床工学技士が医療機器メーカーに入っても基礎知識で苦労することは少ないと思います。その点は新卒、中途採用問わず有利になります。
しかし、医療機器メーカーで必要とされる知識は医療機器に関する基礎知識と製品情報になります。そのため、実際に現場で機械を使ったことがない新卒採用の場合、入社後に製品情報の勉強が必要になります。
また、ここでいう製品情報とは「使い方」や「製品スペック」だけではありません。
- 他社と比較してどうなのか
- 担当エリアでどのくらい採用されているのか
- 施設ごとの医療機器採用理由
- 臨床使用した時の「いい点」、「悪い点」
など、勉強・調査することは盛りだくさん。

ここが「新卒採用」と「中途採用」の差になります。
自社装置を使ったことがある状態で中途採用された場合、
- 臨床使用した時の「いい点」、「悪い点」
が分かっている状態です。
自社装置を使ったことがない状態で中途採用された場合、
- 他社と比較してどうなのか
が分かりやすい状態です。

使用歴は自社・他社問わずメリットになる!!
しかし、「新卒採用」の場合、上記メリットを実臨床で学ぶ機会がほとんどありません。そのため、実際に医療機器が使われている状態がイメージしにくくなってしまいます。

新卒採用だとメリットはないの?
「新卒採用」の場合でも医学に知識があるため、周りと比べてスタートダッシュができますが、
- 周りの新卒は英語が得意
- 経済学を学んでいた
「医療」以外の知識が豊富なケースがあります。そのため、一概に「新卒」有利になるとは言い切れません。
例えば、家電屋さんでパソコンを売るとしたときに、
- パソコンを使ったことがある人
- パソコンを使ったことがない人
どちらが売れるでしょうか。両方とも製品に関する知識量が同じだったとしても
- パソコンを使ったことがある人
のほうがたくさん売れると思います。
それは、パソコンに関する一次情報(実体験など)があるためです。同じことが医療機器でも言えます。現場を知らない人より、現場を知っている人のほうが説得力は増します。

「製品知識」のみならず「臨床」が大事!!
そのため、「中途採用」の場合でも、「臨床」の知識が少ないと苦労することになります。会社側からしても「中途採用」で「臨床工学技士」を採用する場合、「臨床」経験を見込んで採用しているからです。
いろいろな施設を見ることができる
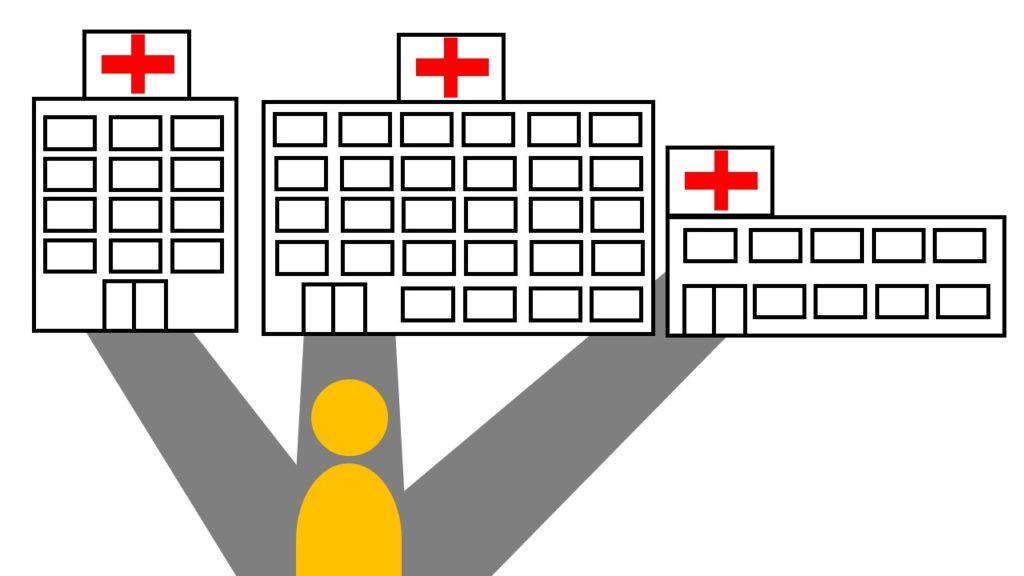
医療機器メーカーは「営業」、「サービス」、「アプリケーションスペシャリスト」業種を問わず、たくさんの施設にいきます。
そのため、おのずとたくさんの施設を見ることができます。
- どのような考え方で医療機器を更新しているのか
- どのような使い方をしているのか
たくさんの施設をみることで臨床工学技士としての視野が広がると思います。これは、病院で仕事をしているとなかなかできません。医療機器メーカーで働くことで得られるメリットの1つだと思います。
病院とメーカー、何が違うの??
「営業」、「サービス」、「アプリケーション」どれをとっても最終的には売り上げが大事になってきます。メーカーは製品を売ることが目的になるため、
- どうすれば売れるのか
を考える必要があります。
病院勤めの臨床工学技士は自分の技術や知識を患者さんのために使います。
言わば、病院に対して「技術」、「知識」を売っています。対してメーカーは病院に対して「製品」を売っています。
「製品」を売るために「技術」や「知識」を使うわけです。つまり、
「技術」・「知識」をそのまま売るのか、はたまた「技術」、「知識」は売るためのツールなのか
が大きく違うポイントになります。
病院勤めであれば「技術」・「知識」を磨けばそのまま評価される傾向にありますがメーカーは「技術」・「知識」をどう使うかが主眼になります。
そのため、「技術」・「知識」が少なくてもたくさん売り上げる人もいれば、「技術」・「知識」が多くても売り上げが伸びない、宝の持ち腐れ状態になることもあります。
そしてつきまとうのが「ノルマ」。
「ノルマ」を達成していなければありがたいお言葉を頂戴し、「ノルマ」を超えていればフィードバックがある。頑張った分だけ見返りがあるのもメーカーと病院の違いとなります。また、個人目標が明確になっていることも病院とは違う点だと思います。
医療機器メーカーでつらいことは?
「売り上げが上がらないとき」
これは想像しやすいと思うので多くは語りません。
同期と話が合わなくなってくる
臨床工学技士は大多数が病院に就職します。
そのため、同窓会やらなんやらで話す際、話が合わなくなってきます。
臨床工学技士の業務は
- 血液浄化
- 人工呼吸
- 人工心肺
- 機器管理
- 不整脈
- 内視鏡
などなど多岐にわたります。
しかし、それら製品を包括して販売している医療機器メーカーは存在しません。そのため、それら業務をしている人たちと話が合わなくなってきます。
また、臨床の話をメインになると、だんだんとついていけなくなります。そのため、若干の疎外感を感じたりします。
いつ連絡がくるかわからない
医療機器メーカーに勤めると個人用のスマートフォンが支給されます。
24時間365日連絡が取れるような状態、つまり病院でいう、常にオンコール
みたいな状態です。
これでは気が休まりません。休日や深夜に連絡が来たりします。これは単純につらいです。
基本的には連絡は来ないですが、連絡がきたときはそれほど緊急度が高いと言えます。
さいごに
昨今の医師の働き方改革による臨床工学技士の業務拡大により、着々と臨床工学技士の業務幅が広がっています。それが、医療機器メーカーにまで広がればいいなと思います。
臨床工学技士が当たり前のように医療機器メーカーに就職することで、病院内外から医療機器を通じて病院を支えることができるためです。
少しでも医療機器メーカーに興味のある方の参考になればと思います。
↓医療機器メーカー転職の場合、こういう転職サイトに登録すると便利です。

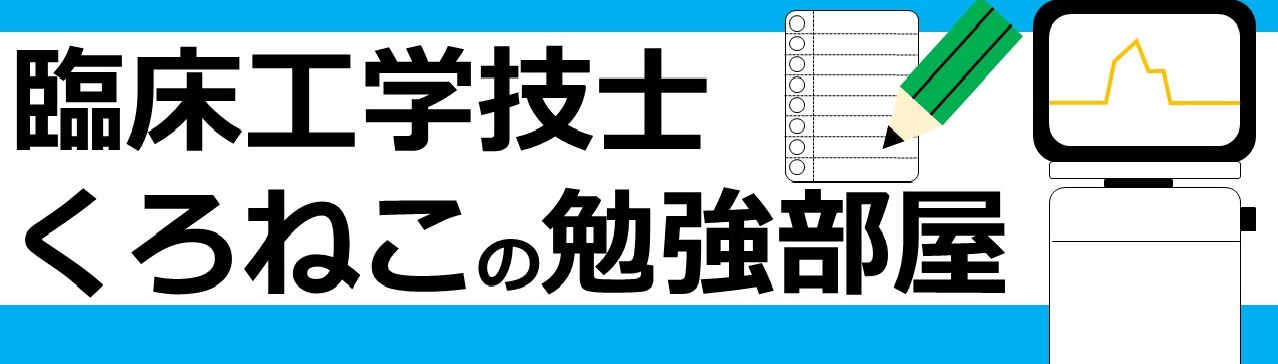





















コメント