
幼女戦記ってなに?
幼女戦記はノベルス、web小説、漫画、アニメ、映画と多数展開されています。エリートサラリーマンだった主人公が魔力を持って異世界に転生し、異世界で魔法を駆使して大戦を経験していく、いわゆる「異世界転生系」です。

だけど、幼女戦記ってタイトルが・・・
タイトルとは裏腹に、なかなかブラックな内容になっています。
- 幼女戦記 1 Deus lo vult:ノベルス
- 幼女戦記(3):コミックス

ターニャがプレゼンについて話しているのはノベルス1巻、コミックス3巻です
プレゼンテーションを学ぶ
幼女戦記の中で主人公であるターニャと、軍上層部(参謀)であるゼートゥーアが今後の戦争形態について話し合う場面があります。その際、主人公のターニャは

いつの時代も上に知己を得ていても損はない。チャンスを活かせ。この機会を最大限利用するんだ。
と、考えています。つまり上にアピールするため、「今後の戦争形態」というお題を通してプレゼンします。そのとき、プレゼンについてターニャが思考しています。
今回はターニャの思考をもとに、プレゼンについて考えていきましょう。
考えの言語化

黙っていても、わかってくれるだろうというのは甘えだ。
これに関しては「確かに」と思いました。日本では「察する文化」が根付いており、「言わなくても分かる」、「相手の考えを察しろ」というのが一般的です。では、なぜ「察する」ことができるのでしょうか。
- こう考えているんだろうな
- この状況だと、これが欲しいんだろうな
- いま機嫌が悪そうだ
など、生活している中で「察する」ことは無数にあります。しかし察するには、いくつもの経験が必要です。
- この表情のときはうそをついているな
- モノが見つからなくて探しているんだな
- この発言をしたら相手の機嫌を損ねた
など、自分の今までの経験や相手との付き合いなどから導き出されます。いわゆる「暗黙知」です。
暗黙知
経験的に使っている知識だが簡単に言葉で説明できない知識のこと
作業など、自分メインの経験であれば、

次はあの作業だから、必要な物品はあれだ。だけど、手に持っていないな。
など、予想つけることが可能です。しかし「ヒト対ヒト」の経験はそうもいきません。相手がいなければ「ヒト対ヒト」の経験はできません。しかし近年では「働き方改革の推進」により、「残業時間」が短くなっています。一昔前では、夜遅くまで顔を突き合わせてい仕事をしていましたが、今はそうもいきません。そのため、職場における「ヒト対ヒト」の経験が少なくなってしまいます。また、在宅勤務なども「ヒト対ヒト」の経験減少に拍車をかけています。
よって「言語」を用いて「自分の考え」を伝えなければ、昔以上に相手に伝わらなくなってきています。

昔以上に「言語化」は重要!!
質問の重要性

相手の質問の意図を確認するという積極性と慎重さを同時にアピールすることこそが出世には不可欠だ。
相手の質問の意図や意味が分からなかったとき、

ん?どういう意味だろう?
と思っても、「どういう意味ですか?」など、質問の意味を聞き返す人は少ないのではないでしょうか。
- そもそも質問するような空気ではない→「心理的安全性の欠如」
- 質問の仕方が分からない
などの問題が様々な原因がはらんでいるいると思われます。
そのため、会議などを開催しても「シーン」と静間にかえってしまうなんてことも・・・
逆を言えば「誰も発言できずにいる状態で発言する」ということは、内容を問わず評価されるということになります。
- 最初に質問することができる人は続く人が質問できるような空気にしていてえらい
- 簡単な質問をする人は、続く人が「こんな簡単な質問をしていいのだろうか」という空気を払拭できてえらい
- 難しい質問をする人はその後の議論に深みが出るためえらい
と、「質問するひとはそれだけでえらい」と私は思います。
共通認識の確立

説明を面倒くさがらないこと。無駄の多い会議を防止するための唯一の解決策は、徹底的な共通認識の確立。
「共通認識の確立」。これは本当に重要だと思います。お互いの共通認識ができていなければ会議の必要はありません。例えば「目的の共通認識」について考えます。今回は3人の「レンガ職人」でみていきましょう。
中世ヨーロッパに3人のレンガ職人がいました。旅人がレンガ職人ひとりひとりに「今何をしているのか」を聞いて回ります。すると以下のような回答が返ってきました。
一人目のレンガ職人
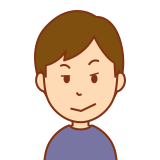
ひたすらレンガを積み上げています
二人目のレンガ職人
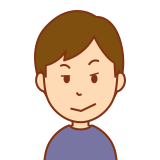
大きな壁を作って、家族の生計を立てています
三人目のレンガ職人
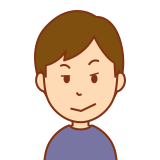
偉大な大聖堂を作っています
三人はそれぞれ「作業内容」、「業務の目的」、「仕事の理念」を答えています。
この三人のレンガ職人が「なぜレンガを積み上げるのか」という会議をしたとしても、
- 一人目は会議開催の意味すら分からない
- 二人目は生計を立てることが目的のため、お給料などの視点になる
- 三人目は立派な大聖堂を建てたいため、どうすれば立派になるのかを考える
と、「レンガ職人」という同じ職種であっても、仕事に対する認識が違うため、話し合うべき内容を話し合えません。
自分たちの仕事の認識ですら各々考え方が違うのに、認識が違う人がモノゴトを見たとき見える景色はどうなるでしょうか。
仕事に対し「業務の目的」という認識をしている人と「仕事の理念」と認識している人へ

新規事業を行う
という方針が立てられたとき、
- 目的→新規事業はめんどくさい
- 理念→新規事業は楽しそう
と考えます。
このように、考え方によってモノゴトに対し齟齬が発生する可能性があるため、会議参加者に対し「共通認識の確立」は大切になります。

予想の断言

予想は断言した方がよい。
- ・・・・だと思います
- ・・・・です
どちらが説得力があるでしょうか。
もちろん「・・・・・です」と、断言しているほうが説得力があります。
プレゼンの目標は
相手に伝える努力をした結果、相手に伝わり、最終的には相手の行動や考え方などを変えること
です。よって、相手の行動・考え方などが変わらなければ意味がないと言えます。
相手の行動を変える際、

・・・・・・だと思います。
・・・・・・だと考えます。
と言うより

・・・・・・・です。
・・・・・・・実施してください。
など、言い切ったほうが相手の行動が変容する可能性が高まります。
要点を伝える

プレゼンは要点を伝えられねば意味がない。
「要点」とは言い換えると「重要な点」です。重要な点を相手に伝えられなければ意味がない、ということになります。無駄な言葉で修飾されると、「重要な点」がぼやけてしまいます。そのため、要点をズバッとまず伝え、そこから相手の疑問にたいして肉付けしていくことが重要です。プレゼンで活用するPREP法などもまずは「結論」を伝え、そこから肉付けしていく手法になります。
PREP法
- P:Point(結論)
- R:Reason(理由)
- E:Example(具体例)
- P:Point(結論)
職責を超えた発言の自粛

そして自らの職責を超えた発言は自粛するべきだ。例えば、人事部が営業に口を挟むべきではないし、営業が人事部に口を出すのも同様だろう。
これはまったくもってその通りです。
- 人事部が営業に口をはさむ
- 営業が人事部に口をだす
こんなことしてもいいことありません。自粛すべきです。口をはさんだところで
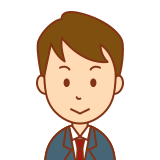
他部署が何を言ってるんだ・・・理解もしてないくせに
と思われることが関の山です。
さいごに
今回は「幼女戦記」からプレゼンテーションについて考えていきました。本作には「プレゼンの方法」など、考えさせる内容が多数出てきます。が、

無駄の多い会議を防止するための唯一の解決策は、徹底的な共通認識の確立。
と言ってるのに、互いの意思疎通がまったくできておらず、アンジャッシュのコントみたいな状態によくなっているのが面白いです。

コミックスのほうが共通認識の確立ができていない状態がより分かりやすく書かれています。
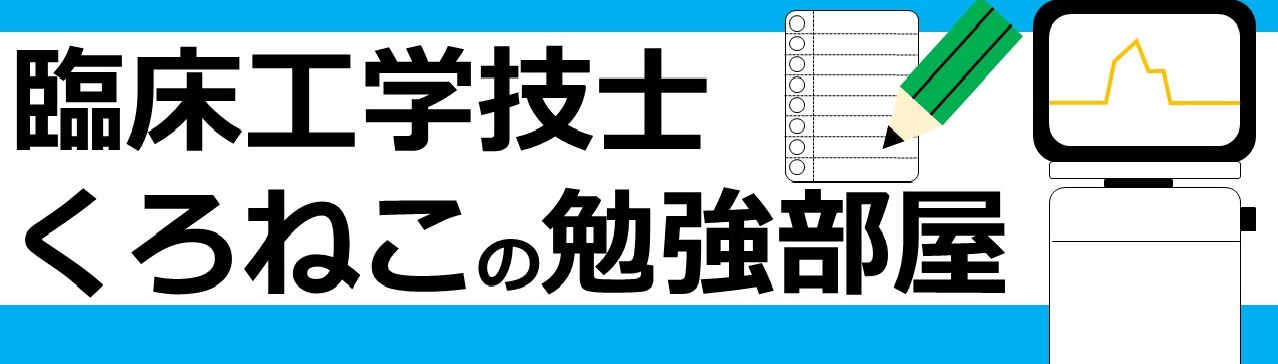
























コメント